学校推薦型における個別学力検査の実施時期の問題について、文科省に聞く
学生募集・高大接続
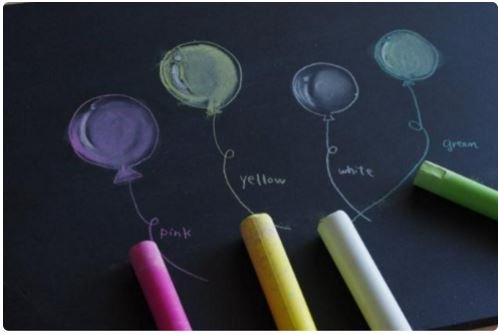
2025.0212
学生募集・高大接続
3行でわかるこの記事のポイント
●学校推薦型選抜としての選考方法と実施時期、2つの問題が複合
●学校推薦型選抜は「年内に合否を出す入試」ではない
●「入試とは何か」という原点に立ち返って検討を
文部科学省は2024年12月、学校推薦型選抜を含む各選抜における個別学力検査の実施時期のルール順守を求める通知を大学宛に出した。これを受け、一部の大学が2026年度入試で予定していた入試の内容やスケジュールを見直すなど、波紋が広がっている。今後、文科省はこの問題にどう対応するのか、所管する大学教育・入試課大学入試室の担当者に聞いた。
質問と文科省の回答は以下の通り。
――12 月 24 日、全国の大学宛に「🔗大学入学者選抜実施要項において定める試験期日等の遵守について(依頼)」という通知を出すに至った経緯とは。
大学入試室には、入試に関する問題の相談窓口などを通じて、実施内容や実施時期を含め、入試に関わるさまざまな問題について情報が入る。
2024年夏頃、具体的な大学名を挙げて「学校推薦型選抜の個別学力検査を2月1日より前に実施しているのではないか」との指摘が複数寄せられ、われわれが調査した結果、事実であることを確認した。
高校と大学の代表者で構成する「大学入学者選抜協議会」 (以下「協議会」)においても、高校側から
・同様の問題は、かなり以前から他の大学の入試でも見られる(これについても、文科省が事後的に確認)
・個別学力検査の早期実施は高校教育に悪影響を及ぼすため、看過すべきでない
・一部の大学については、早期実施に加え、選考方法が多面的評価とは見なせないという問題もある
等の指摘がなされた。
情報提供で個別に名前が挙がった大学については、当該大学から状況等を直接確認のうえ、見直しを求めた。
一方、それら以外の大学でも個別学力検査の早期実施が広がっていることや、高校関係団体を中心とする懸念を重く受け止め、今回の通知によって「大学入学者選抜実施要項」(以下「実施要項」)で定めているルールをあらためて周知し、順守を求めた。
今回、協議会が問題視しているのは「学校推薦型選抜と称しているにもかかわらず多面的評価とは見なせない内容」と「個別学力検査の早期実施」という2点だが、実施要項には「学校推薦型選抜では○○と●●を必須で課さなければいけない」といった規定はなく、各大学の判断に任されている。そのため、通知では、実施要項に明確な規定がある実施時期についてのみ言及した。
前者については、実施要項での規定の有無にかかわらず、本来、学校推薦型選抜とはどのようなものかという観点から問題があると認識している。
――大学には「かなり以前から、他の大学でも同様の実態があったにもかかわらず、なぜ今になって通知が出されたのか」という戸惑いがある。
多くの大学がいくつもの方式で入試を実施していて、毎年何らかの変更が加えられている。文科省はこれらすべての詳細を把握しているわけではない。今回、個別の大学名で実施時期に関する指摘を複数受けたことがきっかけとなって、他大学を含む状況を把握した次第だ。文科省がこうした状況を長く把握できていなかったことを問題視されるのであれば、甘んじて受け止めるしかない。
――学校推薦型選抜の個別学力検査を2月1日より前に実施している大学は「特に対策をしなくても解ける基礎的な問題であり、一般選抜の出題レベルとは異なる」と説明している。
問題の難易度にかかわらず、教科・科目単位で出題する個別学力検査である以上、2月1日以降というルールが適用される。「基礎的な問題」のレベルは大学によっても異なり、「ここまでなら可」といった線引きはできない。
大学が教科・科目単位の試験を早期に課せば高校はそれに合わせて授業進度を調整せざるを得ず、高校教育に多大な影響を及ぼす。そのことをふまえ、高校と大学の合意として実施要項を通知している。
大学は常々、企業による採用活動の早期化が大学教育に及ぼす悪影響を指摘し、配慮を求めている。同様の配慮を高校教育に対してもすべきではないか。
――いわゆる総合問題であれば、「教科・科目単位で出題する個別学力検査」とは異なる扱いになるのか。
総合問題の定義が明確ではないが、複数教科を統合して学力を判断する問題は区分上、個別学力検査に含まれるので、実施要項を厳密に運用するなら2月1日より前の実施は不可ということになる。
しかし現状、総合問題を「教科・科目に関するものではない」と大学が位置づけている場合は、それ以前に実施されているという現状はある。問題の作り方によっては科目ごとの明確な色合いがなくなり、高校の教科・科目の授業との直接的な関係はほぼないと言えるからだ。
例えば、資料を読ませたうえで総合的な思考力を問う問題などは小論文に近いと見なすことができ、2月1日以前の実施も妨げないという考え方だ。
ただし、総合問題と称する入試問題を実際に見てみると、大問ごとに各科目の知識を問う内容になっているなど、総合問題とは呼べないものも見受けられる。それらの扱いについても今後、議論する必要があるだろう。
――基礎学力を把握するために年内からでも実施可能なものとして小論文や口頭試問などが示されているが、多くの大学はこれらによって入学後に求められる学力を把握するのは難しいと考えている。個別学力検査が2月1日以降しか実施できないのであれば、年内に合否を決める学校推薦型選抜では事実上、基礎学力を把握することは不可能ということにならないか。
学校推薦型選抜や総合型選抜は「年内から選考を始めることができる入試」であって、「年内に合否を出す入試」ではない。受験生との適切なマッチングを図るべく、時間をかけて丁寧で多面的な評価をするために年内からの実施が定められている。学力の把握も従来型の個別学力検査だけに頼るのではなく、各大学が新たな手法を開発することが期待されている。
学校推薦型選抜や総合型選抜での学力把握の難しさは容易に想像できるが、それでも大学の工夫次第でやり方はあると思うし、国語や数学の試験を課さずとも「自学で受け入れても問題ない学力だ」と判断することはあり得るのではないか。
「いや、入学後のことを考えるとやはり数学の力は見ておきたい」ということであれば、共通テストを課すか、2月以降に独自試験を実施したうえで合否を決めるというのが現在のルールだ。
年内に合否を出すのが当たり前になっている現状は、学生確保を目的とした大学側の都合によるものではないか。大学と受験生との丁寧なマッチングという学校推薦型選抜の本質の部分が骨抜きにされ、「年内に実施できる」という部分だけが都合良く運用されているとすれば、それを見過ごすわけにはいかない。
――学校推薦型選抜の合否判定を年明けに持ち越すと、一般選抜と並行して走ることになり、定員に対して過不足のない合格者数の調整が難しくなる。
どの大学でも入試方式は複数あり、実施時期が遅いものはそれ以前に合格が確定した人数をふまえて合格ラインを決めているはずだ。
――今回の通知のフォローとして、次年度の各大学の学校推薦型選抜における個別学力検査の実施時期にルール違反がないか確認するのか。
現時点でその考えはない。ルールを発信している立場から、今回あらためて「ルールを守ってほしい」との通知を出したが、違反を取り締まる"入試警察"のようなことはしたくない。各大学が良識と責任の下で主体的に判断するよう期待している。
――今後、実施要項に反する場合は補助金配分等におけるペナルティもあり得るのか。
ないとは言えない。
ペナルティを抑止力にしてルールを守らせるというやり方はわれわれの望むところではないが、そこまでしないと難しいという状況になれば、様々な選択肢を検討することとなる。
これまでも、個別学力検査の実施時期を守らない大学は補助事業に申請できないようにしている。今後、同様のことをする場合もわれわれだけで決めることはできず、関係部署との調整や議論が必要になる。
そもそも、現在のルールがそのまま次年度の入試にも適用されるとは限らない。これだけ大きな問題になった以上、ルールをどうすべきか協議会で議論される予定だ。
その結果、「今のルールを維持すべき」という方向でまとまることも当然考えられるが、学校推薦型選抜で学力を把握しやすくなるようルールを見直そうという方向に行く可能性もゼロではない。
かつて、AO入試が「学力不問の青田買い」と批判されたことを考えれば、学校推薦型選抜で基礎学力を把握したいというのは、大学のあるべき姿勢とも言える。そういった姿勢と高校教育の尊重との折り合いをつけられる画期的な提案を大学が出せるのかがポイントになるだろう。高校側には、時期の前倒しは絶対に認めないという強固な意見もあり、その壁を突き破るのはかなり難しいとは思うが。
――最後に、大学に対するメッセージを。
この問題を考える時に立ち返るべきは、そもそも入試とは何かということだ。高校での学びを終えた生徒たちの学びの成果を確認し、それぞれの大学に進学するために必要な力があるか判断することが入試であるはずだ。
であれば、高校での学びが不完全な時期に行うものは入試とは呼べない。そうした共通認識の下で実施要項ができている。
文部科学省としては、高大接続の仕組みを時代に合わせて進化させ、若者一人ひとりにとってのより良い学びを実現するための仕組み作りを進めていくことが重要であると考えている。18歳人口の減少が一層加速する中で、どのような入学者選抜であるべきなのか、引き続き、関係者からの声に耳を傾けつつ、丁寧な議論を進めていきたい。