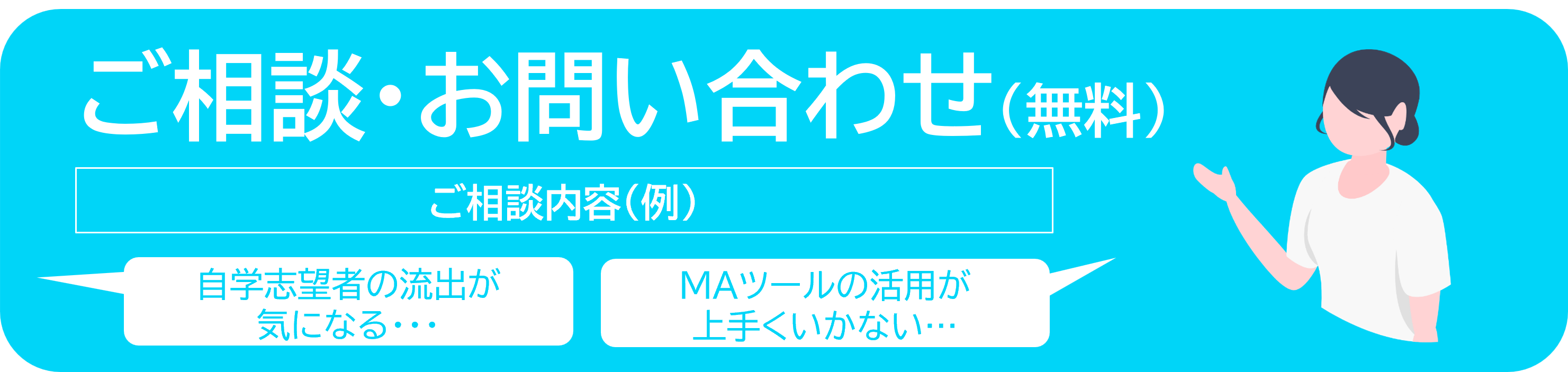〈共に挑む学生募集DX〉vol.02 第一志望層の流出防止から定員充足へ。共栄大学のMA活用の軌跡
学生募集DX

2025.0930
学生募集DX
3行でわかるこの記事のポイント
・第一志望層の流出という課題を克服し、出願数の安定と定員充足を実現
・旗振り役と日々の運用がかみ合い、"毎日30分"の習慣化でMA活用が定着
・「親しみやすさ」を武器に、高校生・保護者からの反応が増加
少子化や高校生の多様化が進む中、大学にとって、自学を志望する高校生との関係を入試まで継続的に育てることの重要性が高まっている。共栄大学では、オープンキャンパスで「第一志望」と答えた高校生が出願段階で他大学に流れてしまうという課題があった。学務部入試課兼学長室 主任の安齋裕之氏と入試課の佐山雄哉氏はこの課題に向き合って接点を途切れさせないナーチャリング基盤を整え、学内の役割分担と運用の習慣化を進めた。その結果、流出は大きく減少し、定員充足にもつながった。さらに、高校生や保護者からの返信や感謝の声が増え、現場のモチベーションも高まっている。本記事では、共栄大学が取り組んだ学内合意形成のプロセス、業務効率化とデータ集約の効果、そして同大学らしい「親しみやすさ」を生かした広報について紹介する。

共栄大学が募集課題解決のために導入したのは、学生募集MAツール infoCloud Digital Marketing + である。今では活用が進み成果を上げているが、検討から導入に至るまですべてがスムーズに進んだわけではなかった。導入当初にまず直面したのは、職員間での理解や習熟度のばらつきだった。入試課の職員6名の中には、新しいツールの操作に不慣れな者や、「なぜMAツールを使う必要があるのか」という目的理解に戸惑いを持つ者もおり、足並みをそろえることが大きな課題となっていた。
こうした不安を解消するきっかけとなったのが、進研アド営業担当の提案で訪問した戸板女子短大での事例視察である。実際の画面を用いた運用方法の説明や、イベント前後にメールを送るといった配信タイミングの工夫を確認できたことで、安齋氏は「自学でも具体的にどう進めればよいか」をイメージできたと振り返る。単なるマニュアルではなく、同じように運用に悩んだ大学の取り組みを"見せてもらえた"ことが、学内に説明する際の大きな支えとなったという。
さらに安齋氏は「システムは使用しないと、慣れることはない」と考え、戸板女子短大で実践されていた「毎日30分は必ずシステムを見る」というルールに共感し、自学でも導入することを決断。自分だけでなく入試課全体に呼びかけ、日々システムに触れる習慣をつくった。こうした"実際に使う体験"を重ねる中で、少しずつ使いこなせる職員が増え、導入当初は不安や抵抗もあったMA活用が、半年から1年をかけて「使っていこう」という共通認識へと変わっていった。
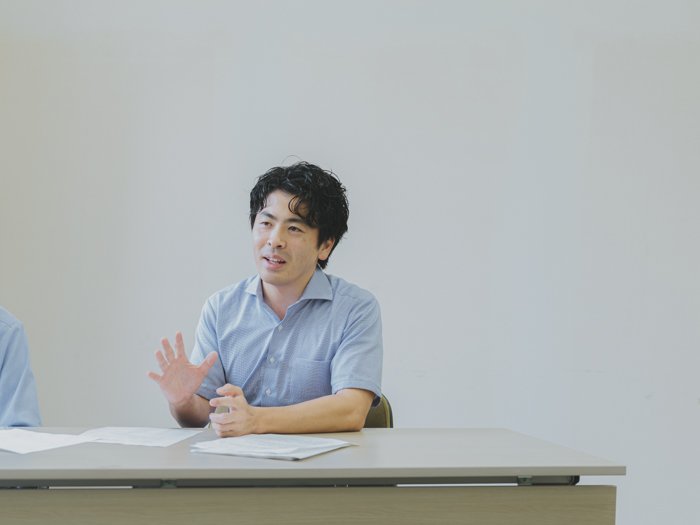
MAツール導入の効果は、まず業務効率の大幅な改善に表れた。従来はオープンキャンパス参加者に一人ずつ手書きでお礼状を送っていたが、今ではメールやLINE配信で自動化できるようになり、職員の負担は大きく軽減された。また、オープンキャンパスの申し込みやアンケート回答、LINEでのやり取りなどを一元管理できるようになり、「誰がどの高校生とどんなやり取りをしたか」が一目で分かるようになった。さらに、開封率やクリック率、返信率といった反応データも蓄積されるため、発信の効果測定や改善の判断材料として活用されている。
現在の主たる運用を担うのは、入試課の佐山氏だ。日々の配信設計やデータ活用を自らハンドリングしながら、「成果が見えることで職員同士の会話が変わった」と話す。以前は"やるべき業務"として取り組んでいた発信も、今は「どの高校生にどう届いたか」を基点に議論できるようになった。職員がそれぞれ担当する発信の開封率や返信内容を共有し合い、「どうすればもっと響くのか」と切磋琢磨する雰囲気も生まれている。
こうした運用改善の裏側で、進研アドの営業担当が定期的に高校生の声や他校の事例など、現場の工夫に役立つ視点を提供してきた。佐山氏は「成果に直結する発信を行えるようになり、広報が高校生とつながる実感を持てるようになった」と語る。単なる業務の省力化にとどまらず、外部パートナーと現場が一緒に改善を積み重ねてきたことで、広報の質そのものを高める基盤ができあがった。

共栄大学の教育面での強みは、少人数教育を通じた"面倒見の良さ"だ。その特色が、広報活動においても体現されている。職員一人ひとりが「親しみやすさ」を前面に出し、きめ細かなコミュニケーションを心がけている。メールやLINEでは地域の地元特産品や職員自身の趣味にちなんだ絵文字を入れるなどの工夫も見られる。
こうした発信に対して、高校生や保護者からは「親しみを持てる」「大学が身近に感じられる」といった内容で返信が増えるなど、双方向のやり取りが定着してきた。教育の現場で培われた"面倒見の良さ"が広報でも自然に表現されることで、大学全体の魅力をより実感してもらうという効果につながっている。
結果として、大きな課題となっていた第一志望層の流出は大幅に減少し、出願数も安定。定員充足に直結する成果を上げることができた。さらに、入試直後に送ったメールやLINEでは、「受験おつかれさま」「体調に気をつけて」など受験生の気持ちに寄り添ったメッセージを発信。その結果、「ありがとうございます」「安心しました」といった返信が届くようになり、職員が「広報の手応え」を実感できる場面も増えている。こうしたやり取りは数値には表れにくいものの、現場のモチベーションを押し上げ、日々の業務に向けた前向きな原動力となっている。

現在は、低学年の接触者から取得している「希望する学び」の情報をもとに、進級後にその関心に合った模擬授業を案内する取り組みを強化している。高校生の興味関心を起点に接点を設計することで、入試期まで関係を継続できる仕組みをさらに向上させる方針だ。こうしたナーチャリングによって志望度が高まり、第一志望層の流出防止や出願数の安定といった数の成果が表れている。また、メールやLINE配信における開封率や返信率が着実に改善し、職員同士でデータを共有して議論する文化も育ってきた。「どうすればもっと響くか」という前向きな試行錯誤が広がり、現場にとっても"広報が高校生とつながっている実感"が増しているという。
数値化できる成果に加え、"親しみやすさ"や"安心感"といった情緒的な価値も積み重なっている。高校生や保護者から「大学が身近に感じられる」「やり取りが丁寧で安心できる」といった声が届き、双方向の関係性が定着しつつある。
その先にあるのは、高校生が入学前から「自分のことを理解し、成長させてくれる大学」と実感できること。入試課の安齋氏や佐山氏を中心に、職員一人ひとりが寄り添う姿勢を広報活動でも体現することで、共栄大学はこれからも"選ばれる理由"を学生とともに育てていく。
写真左から、共栄大学 学務部入試課の佐山雄哉氏、学務部入試課兼学長室 主任の安齋裕之氏
(文・写真:大坪 侑史)
進研アドのMAツールに関する相談は
共栄大学のように、学生募集やMAツールの活用定着に課題を抱えている大学は、実際の活用事例や最新機能を体感できる学生募集MAツール infoCloud Digital Marketing +の「無料の相談会」をぜひご活用ください。