全学年でのアセスメント実施により教学マネジメントを推進-北海学園大学
ニュース

2024.0624
ニュース
3行でわかるこの記事のポイント
●入学前から告知に力を入れ、1年生の受検率は90%超
●キャリア支援センターや将来構想委員会もデータを活用
●担当副学長の下でアセスメントポリシー、アセスメントプランを策定
北海学園大学は「教育力で選ばれ続ける大学」をめざし、教育成果の可視化を起点とした教学マネジメントに取り組んでいる。そこで活用しているのが、アセスメントテスト「GPS-Academic」だ。全学年で実施し、学生の成長を精緻に分析していく。
北海学園大学(札幌市)は経済、経営、法、人文、工の5学部で構成され、1学年約2000人の学生がいる。北海道を代表する私立大学で、国公立大学との併願者も多い。
同大学は、2018年度からベネッセi-キャリアが提供するアセスメントテスト「GPS-Academic」を導入。当初は1年生のみが対象だったが、2年生、3年生へと段階的に拡大し、2023年度からは全学年で実施している。
2023年度、1~3年生は4月~5月、4年生は夏休み明けから9月にかけ、いずれも1か月程度の期間を設けて各自、都合の良い時にオンラインで受検してもらう。
導入の最大の目的は、教育成果の可視化だ。
大学全体で学生募集が厳しくなる中、現在のポジションに安住することなく、知名度や偏差値よりも教育力によって選ばれる大学であり続けたいと考えた。
絶えず教学改善を図っていくために、まずはディプロマ・ポリシー(DP)の達成度を明らかにしようというわけだ。
北海学園大学では、2人いる副学長の1人の所管業務に内部質保証を加えた2022年以降、教学マネジメントに従来以上に力を入れている。
同年には、学修成果を検証するための全学のアセスメントポリシー、および同ポリシーに基づく学部ごとのアセスメントプランを策定。これらの中で「GPS-Academic」や各種アンケートなど、学修成果測定ツールの活用を規定した。
2023年度から「GPS-Academic」で全学年のデータが取得できるようになり、今後はその本格的な分析に入る。アセスメントを所管する学習支援システム課の田口聖志課長は「全体として、DPで掲げる力がおおむね身に付いていることはわかった。全学年実施2年目となる今年度の結果とも比較するなど、多面的に分析していきたい」と話す。
一方、各学部はそれぞれのアセスメントプランに基づき学部レベルの教学マネジメントのPDCAを試行している。成績不振者対象の個別面談や、導入から数年が経過した基礎ゼミの見直しにおけるデータ活用が当面の課題となりそうだ。
「GPS-Academic」の導入から7年がたち、活用の場面は広がっている。
キャリア支援センターでは3年次以降、就職活動における「自己分析セミナー」などで個人データを活用するよう指導。また、各企業が採用において求める資質・能力を「GPS-Academic」の指標で表し、就職活動の参考資料として学生に提供している。
学長も加わる学内最上位の審議体「将来構想委員会」は、学習支援システム課IR担当がまとめた「全学部IRデータ」「学部別IRデータ」に基づき、GPS-Academicで測定された思考力や姿勢・態度、経験を入学年度別、入試区分ごとに確認している。
また、GPS-Academicの結果を基にした学生の成長度合いのグラフを受験生サイトに掲載。「カリキュラムがどのような成長につながるか」というデータを入試広報に活用している。
北海学園大学では、学生の実態を正確に捉えるため「GPS-Academic」の受検率向上に力を入れている。1年生の受検率を特に重視し、さまざまな告知活動を展開。
一般選抜の合格発表後に立ち上げる新入生特設サイトで、アセスメントテストの目的を説明して実施を予告。ベネッセi-キャリアが制作した🔗「GPS-Academic」紹介動画にリンクを貼っている。
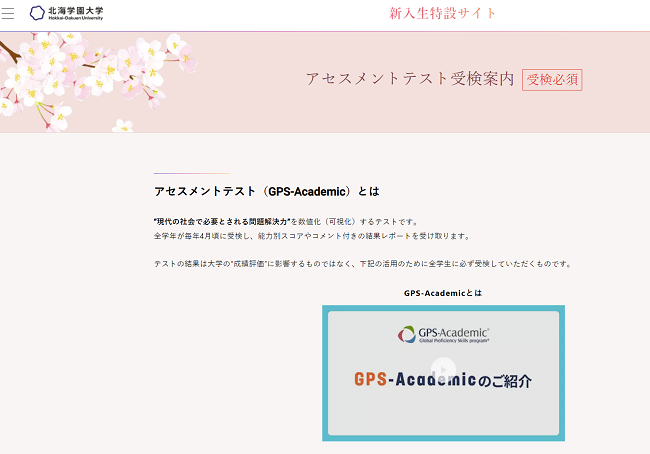
入学後は、学内のポータルサイトや学内各所に掲示を行うなど、受検を促す発信をしている。さらに、各種ゼミナールの担当教員が授業で受検を呼びかける。
こうした取り組みによって、1年生の受検率はほぼ毎年90%台で、同規模の大学に比べてかなり高い。
田口課長は「100%をめざし、受検結果のデータが大学のどんなサポートにつながるかなど、より丁寧な説明に努めたい」と話す。
教学マネジメントを推進するうえで、データ分析を担うIR体制の整備が課題となる。経営学部には独自のIR委員会があるが、それ以外の学部では教務委員や入試委員がデータの分析を担当。全学的なIR組織を求める声も挙がっているという。
「GPS-Academic」をはじめとする各種データの学生や教員へのフィードバックも、今後の課題として具体的な手法が検討される。
北海学園大学では現在、教員や企業を対象とするものを含め13の調査を実施。「GPS-Academic」のデータは、学生に主体的な学修を促すために個々にフィードバックしているが、多様な調査を網羅した総合的な分析結果は提供できていない。教員に対しても一部の公開にとどまっている。
田口課長は「教員、学生の協力によってさまざまなデータが蓄積されている。適切な管理の下、可能な限り全学で共有し、教育力の可視化とさらなる向上につなげることが重要だ」と話す。